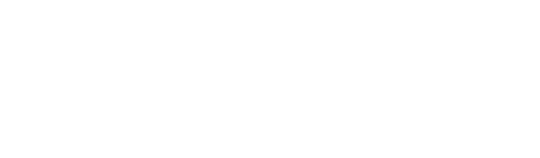2025-11-05 17:44:08 配信
「津波防災の日」全国で緊急地震速報訓練 専門家は一人一人が防災を考える必要を訴え
 5日は「津波防災の日」です。この日に合わせて全国各地で緊急地震速報に対応する訓練が行われ、参加した自治体では実際に避難先まで移動するなど地震への備えを見直しました。
5日は「津波防災の日」です。この日に合わせて全国各地で緊急地震速報に対応する訓練が行われ、参加した自治体では実際に避難先まで移動するなど地震への備えを見直しました。茨城県高萩市は大きな地震が来た想定で緊急地震速報への対応をした後、津波警報が出た想定で住民が高台へ集合し、市が協定を結んだ企業の建物に避難する訓練を行いました。
7月に起きたロシアのカムチャツカ半島付近での地震では、高萩市に津波警報が出ました。
その際、高台に集まった人の多くが民間の企業の建物への避難をためらって外にとどまっていたことを受け、改めて手順を確認したということです。
住民
「自分自身が体験しないとと思って。90歳近いんですけども来ました」
「お墓の脇にじっとして暑さ寒さに耐えるのは大変なことなんです」
「(Q.建物に避難できるのは?)こういうのっていいですよね。提供して下さる会社があるのは本当に心強い」
地震への備えについて、防災の専門家は「特定の行動を繰り返す訓練では思考停止になる」と警戒感を示しています。
事前に予告をしないで緊急地震速報の訓練をした時の映像では、警報を聞いた子どもたちは迷いながらも10人ほどが校庭に残りましたが、多くは一斉に校舎に戻りました。
日本大学危機管理学部 秦康範教授
「子どもはやっぱり地震の時は、机の下に潜りなさいという指導を忠実に守った結果だと思う」
動画を撮影した秦教授は本来であれば倒れるものが少ない校庭の中央に集まる方が安全だとして、避難行動自体が目的になってしまっていると指摘しました。
研究チームは災害時には周りの状況を見極められるよう、顔を上げて転倒しないように安定した姿勢を取り、落下するものなどに備えてほしいとしています。
日本大学危機管理学部 秦康範教授
「従来は特定の行動を繰り返し繰り返しやるので、どうしても思考停止になっていた。求められているのはどこで地震が起きるか分からないので、どこにいたとしてもそこでどんな危険が起こり得るか、きちんと危険を予測できること、そのうえでどうやって身を守るか危険を回避する」
そのうえで、秦教授は災害は大人がいない時間に起きる可能性もあり、安全な環境を整備したうえで「子どもと先生が話し合って危険を想定してほしい」としています。
訓練を手軽に行うための取り組みも始まっています。
気象庁は先月から緊急地震速報の訓練用の動画を公開しました。
気象庁緊急地震速報技術開発 野口恵司係長
「実際に行動して経験を積んでいただく。いざという時にも慌てずに身の安全を守る行動を取れるようになっていただきたい」
LASTEST NEWS