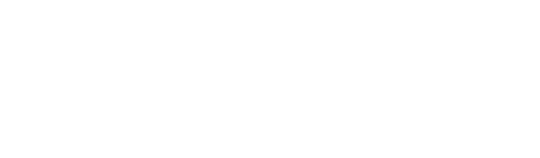2025-04-28 配信
常磐線の歴史を紐解く「探検ツアー」 参加者だけに公開された遺構とは…(福島)<BR>
ゴールデンウイーク前半、普段は利用する人が少ない南相馬市の駅に県内外から多くの人が集まりました。駅から出発したのは「探検ツアー」。
参加者が特別に見学した常磐線の歴史を紐解く遺構とは?
JR常磐線の駅では最も乗り降りする人が少ない桃内駅。
26日、首都圏など県外からの参加者を中心におよそ30人が集まりました。
参加した男性
「横浜からもう。(午前)4時起きです」
「廃線に興味持ってて、数年前からずっと、こういうツアーがあったら参加するようにしているんですよ」
ツアーの目的は、隣の小高駅との間にある今は使われていないトンネルなどの見学。
4月から県内で始まった大型観光キャンペーンのプレ期間に合わせて、JR東日本水戸支社が企画しました。
一行がやって来たのは、国内初の民間鉄道会社「日本鉄道株式会社」が、明治時代に建設した当時の磐城線の4つのトンネル。
いずれもレンガ造りで、蒸気機関車が走っていた頃の遺構です。
記者リポート
「以前使われていたトンネルの中なのですが、上の方を見てみますと、色が黒くなっているのが分かります」
トンネルの内側が黒くなっているのは、蒸気機関車から出るすすや熱によってレンガの色が変わったため。
参加した人たちは、トンネルの壁を触って感触を確かめながら、鉄道の歴史に思いを馳せました。
そして、トンネルの見学と合わせて行なわれたのが、桃内駅から歩いて5分ほどの場所にある防空壕の見学です。
記者リポート
「防空壕の中は非常にひんやりとしていて、部屋の中に入ってみますと、(天井の)高さはそんなには低くないといった印象です」
国の登録有形文化財の「天野家住宅」の敷地にある防空壕は、内部が5つの部屋に分かれていて、合わせて60平方メートルほどの広さがあります。
大規模な防空壕は、周辺の住民も一緒に避難できるように作られたとみられ、今回初めて公開されました。
参加した男性
「当時の防空壕も本当にこうだったのかなという感じでしたね。中は結構狭いようで広くて」
参加した女性
「自分の命の安全のために地域の人みんなで協力して、あそこまで広い防空壕を作ったのかなって思って。すごいなって思いました」
参加した女性
「お茶碗とか落ちてましたし、その中で小さい子どもとか守りながら過ごしてた人たちのことを思うと、面白おかしく見物するものじゃないなって」
見学した人たちは終戦から80年を迎えるのを前に、戦時中の暮らしぶりを垣間見て当時の苦労をしのんでいました。
参加者が特別に見学した常磐線の歴史を紐解く遺構とは?
JR常磐線の駅では最も乗り降りする人が少ない桃内駅。
26日、首都圏など県外からの参加者を中心におよそ30人が集まりました。
参加した男性
「横浜からもう。(午前)4時起きです」
「廃線に興味持ってて、数年前からずっと、こういうツアーがあったら参加するようにしているんですよ」
ツアーの目的は、隣の小高駅との間にある今は使われていないトンネルなどの見学。
4月から県内で始まった大型観光キャンペーンのプレ期間に合わせて、JR東日本水戸支社が企画しました。
一行がやって来たのは、国内初の民間鉄道会社「日本鉄道株式会社」が、明治時代に建設した当時の磐城線の4つのトンネル。
いずれもレンガ造りで、蒸気機関車が走っていた頃の遺構です。
記者リポート
「以前使われていたトンネルの中なのですが、上の方を見てみますと、色が黒くなっているのが分かります」
トンネルの内側が黒くなっているのは、蒸気機関車から出るすすや熱によってレンガの色が変わったため。
参加した人たちは、トンネルの壁を触って感触を確かめながら、鉄道の歴史に思いを馳せました。
そして、トンネルの見学と合わせて行なわれたのが、桃内駅から歩いて5分ほどの場所にある防空壕の見学です。
記者リポート
「防空壕の中は非常にひんやりとしていて、部屋の中に入ってみますと、(天井の)高さはそんなには低くないといった印象です」
国の登録有形文化財の「天野家住宅」の敷地にある防空壕は、内部が5つの部屋に分かれていて、合わせて60平方メートルほどの広さがあります。
大規模な防空壕は、周辺の住民も一緒に避難できるように作られたとみられ、今回初めて公開されました。
参加した男性
「当時の防空壕も本当にこうだったのかなという感じでしたね。中は結構狭いようで広くて」
参加した女性
「自分の命の安全のために地域の人みんなで協力して、あそこまで広い防空壕を作ったのかなって思って。すごいなって思いました」
参加した女性
「お茶碗とか落ちてましたし、その中で小さい子どもとか守りながら過ごしてた人たちのことを思うと、面白おかしく見物するものじゃないなって」
見学した人たちは終戦から80年を迎えるのを前に、戦時中の暮らしぶりを垣間見て当時の苦労をしのんでいました。